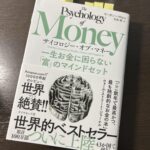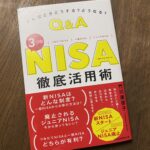2021/08/13

東洋経済オンラインに大江英樹さんの記事がありました。
個人型確定拠出年金の金融機関の選び方についての記事です。参考になる記事ですので紹介したいと思います。
sponsored link
30年の手数料で86万円の差になる
この記事は、個人型確定拠出年金の選び方が重要であることを指摘しています。
この記事のいいところは、具体的な数字で手数料の違いを示してくれているところです。
個人型確定拠出年金でサラリーマンが国内株式型で30年運用した場合、信託報酬の違いが約86万円になるとしています。
仮に30歳から60歳までの30年間、個人型DCに加入して、サラリーマンの積み立て上限額である月額2万3000円を掛け続けたとします。積み立て金額の累計は828万円になります。
仮に国内株式型で最も高い手数料の商品で運用を続けた場合、支払う手数料の合計額は約110万円。これに対して最も安い手数料の商品の場合だと、その金額は約24万円となります。何と4.5倍もの開きがあり、金額でいうと86万円の差にもなります。
前述の口座管理料の場合、その開きは最大でも年間5700円でしたから、同じ30年間でもその差は17万1000円です。信託報酬の差86万円というのがいかに大きな差になるかが、おわかりいただけると思います。
これは、国内株式型の投資信託で、信託報酬が最大0.86%の投資信託と最小0.19%の投資信託を比較した違いだそうです。
数字で明確にしてくれているので、信託報酬の低い商品があるかどうかが、個人型確定拠出年金の金融機関を選ぶ際の重要なポイントだということがわかります。
投資信託の信託報酬に注目しよう
山崎元さんも、著書「確定拠出年金の教科書」のなかで、個人型確定拠出年金の地雷商品に気をつけるように促しています。
個人型確定拠出年金の場合、金融機関によって選べる商品が決まってしまいます。
秋以降は各社で口座開設キャンペーンなどが始まる思いますが、知らないままになんとなく金融機関を選ぶと、手数料が運用成績の足を引っ張るという可能性が高いわけです。
個人型確定拠出年金の金融機関は150社以上ありますが、ストライクゾーンは広くありません。
金融機関を賢く選んで、個人型確定拠出年金の税制メリットを受けられるようにしたいですね。