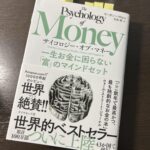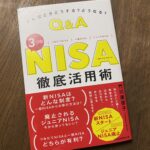2021/08/13

日経新聞に目を通していると、「投資と仕事に活きる言葉」に出会うことがあります。こうした言葉についても、たまにブログで取り上げてみることにしました。
今回は、今朝の日経新聞にあったディー・エヌ・エー(DeNA)の南場智子さんの「思考の独立性」というお話です。
sponsored link
大事にしたい「思考の独立性」
南場智子さんが大事にしているのは、「思考の独立性」だといいます。
採用の際にすごく大事にしているのが「思考の独立性」。私は父の“支配下”にいて自ら考えなかった。親の言うなりという人は少ないが、先生や友達、マスコミなどいろんなものに支配され思考の独立性を失っているように思う。会社も、会長や社長が「答え」だと思ってしまうとバランスを欠いた組織になる。
日本人は「答えは一つ」という教育を受けてきた。高度に均質化した工業製品をつくっていたころはそれがベストだったが、今は邪魔になる。自分で考えて答えを導き出す訓練を積む必要がある。常識や過去の事例から導き出せることはすべて人工知能(AI)ができる時代。人間は新しい課題をどう解決するかという仕事をすべきだ。
DeNA社の社員選考の基準は、「思考の独立性」と「逃げずにやり抜く力」だそうです。
これからの時代、「答えは一つ」と考えるのではなく、「新しい課題をどう解決するか」という問題解決能力が重要になります。
社会の問題を解決できるような能力を継続して磨いていくことが、これからの時代を築いていくうえで重要な能力になります。
答えは一つではない
この話は、投資の世界にも通じる言葉かもしれません。
投資は、未来の経済成長にお金を託す行為ですから、将来の株価や成長する投資信託や個別株といったことについて、確実なことは誰にもわかりません。
インデックス投資の場合も、アセットアロケーションをどうするか、どのインデックスファンドを選ぶかも、人それぞれで答えが一つに決まるわけではありません。
アセットアロケーションを自分自身で決めるのもいいですし、合理性を優先して低コストのバランス型投信1つを選ぶのもいいと思います。
要するに、大事なのは自分で考えて投資するということです。
唯一はっきりしているのは、コストはリターンに影響するということくらいでしょうか。
昨日のロボ・アドバイザーの話と完全に逆行しているような話になりますが、現在のロボ・アドバイザーでは、個人に合わせた最適解を導くことはまだ難しい状況です。
投資もひとつの人生経験です。積立投資も自分で考えていろいろやってみると、見えてくることがあります。
投資という行為は、思った以上に自己の成長につながる経験だというのが、私の最近の実感です。