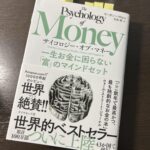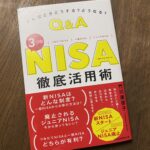2021/08/13

2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震は、一部の地域に大きな被害をもたらしました。
被災された方とご家族の方にお見舞い申し上げます。
今回の地震により北海道全域で1日以上停電したことで、私自身もいろいろと経験することになりました。
そこでこの数日を振り返りつつ、北海道胆振東部地震で準備してよかったもの、足りなかったものをまとめてみたいと思います。
sponsored link
目次をタップすると見出しにとびます
2018年9月6日3時8分
2018年9月6日、普段と同じように寝ていたところ、スマホが突然なりだして「地震です」の声。
その大きな音声で起きると同時に、グラグラと揺れ出しました。2018年9月6日3時8分のことです。
わが家の地域は震度5程度だったそうです。
本棚などの家具には地震対策がしてあります。本棚や食器棚からは特にものが落ちることはありませんでした。
被害はない様子だったので、そのままもう一度寝ることにしました。
停電を知りお風呂と鍋に水を確保
その後、寝ていると妻から「停電した」との声。3時40分過ぎだったと思います。
停電があるなら断水もあるかも…と思い、すぐに起きてお風呂と鍋に水を貯めました。
水の確保は重要です。断水してからではトイレの水も飲み物も確保できませんので、水を確保することは事前に考えていた行動のひとつです。
結果的に断水にはなりませんでしたが、即座に行動して準備したのは安心につながる行動だったと思います。
準備しておいてよかったものリスト
家さえ無事であれば、2人の子どもが5歳と1歳と小さいこともあり、地震後も家で過ごしたほうが生存戦略としてはよさそうだと思っています。
以前から防災には関心があったので、ある程度は意識して用意していました。
事前に準備していたもので利用したのは下記のものです。
現金
地震当日は停電でクレジットカードや電子マネーは使えませんでした。現金はもっておいてよかったです。特に、お釣りがあるとは限りませんので、1000円札や小銭が重宝します。
家には数万円の現金は非常時用で用意してありました。ATMが使えないというニュースもありましたので、停電が長期化しても対応できるように自宅に非常時用の現金を用意しておいたのはよかったです。
水
水道水を鍋で確保しましたが、2リットルのペットボトルは防災用に6本備蓄していました。
断水はしなかったので、ペットボトルの水は使いませんでしたが、次の順番で水は利用するつもりでした。
水道水→鍋の水→ペットボトル
鍋の水もできるだけ備蓄したので、仮に断水しても数日は持ちそうな体制にはしてありました。
結果としてペットボトルの水を利用することはありませんでしたが、長期化したら6本では足りないかもしれません。
食料
冷蔵庫の食品と、普段から食べている缶詰やレトルトはそれなりにありました。
おそらく4人家族で1週間はなんとかなるかなと思う量はありました。
レトルトなどで普段から食べ慣れているものを非常食としていつも多めにストックしておくのは賢い方法だと思います。
カセットコンロ
今回は1日ちょっとの停電でしたが、備品のなかではカセットコンロが特に心強かったです。
カセットコンロを用意しておいたのはよかったです。お湯も沸かせますし、調理も可能です。
日常でも家で鍋をすることもできます。
電気がなくともあたたかいものが食べれるようにしておくのは、安心感が違います。
カセットボンベ
カセットボンベは10本程度用意していました。
じつはカセットボンベを購入したときはこんなにいるかな…とは思っていましたが、実際に地震になるとカセットボンベを入手することは一時的に難しくなります。
それなりの本数があったので、1週間はもつだろうという安心感はありました。
LEDライト
子どもの自転車用に購入していたUSBで充電できるLEDライトも、充電すれば何度でも使えて、一番光が強いということで利用価値がありました。
USB充電式のライトは便利だというのが私の実感です。パソコンに挿して、パソコンのバッテリーから充電することもできます。
電池もあっという間に売り切れになっていたそうですので、電池を使わなくてもUSBの充電で利用できる製品は、思いのほか利便性があると思います。
電池式ライト
電池式のライトは持っていましたが、期間が短かったこともありあまり出番はありませんでした。
ですが、家族に1人1つのライトがあってもいいかもしれませんね。
モバイルバッテリー
モバイルバッテリーは、普段から鞄に入れていて、パソコンの充電やスマホの充電で重宝しています。
停電が続けば後半に出番がくると思っていましたが、持っていると普段から便利なグッズです。
ラップ
今回、断水がなかったので出番は少なかったですが、あると便利なのがラップです。食器にカバーすれば、洗う必要はなくなりますし、衛生面の管理も楽になります。
これはある程度ストックしています。
この他にも、トイレットペーパーやティッシュなどいろいろありますが、少なくとも今回の地震までに意識して準備していたのは上記のものでした。
スマホはパソコンのバッテリーから充電できる
ポイントになるのはスマホの電源です。
スマホは省エネモードで利用することにしました。
スマホの充電が気になるところですが、パソコンからUSB接続で充電できるか確かめたところ、電源がなくてもパソコンのバッテリーからスマホを充電できることがわかりました。
私はiPhoneですが、USBで接続すればiPhoneはパソコンのバッテリーから充電ができます。
わが家には古いのも含めると、ノートパソコンが3台ありますので、パソコンのバッテリーを使ってスマホを充電すれば1週間は持ちそうだなと思いました。USB式のライトもパソコンから充電しました。
長期になることも想定して、最初はパソコンのバッテリーで充電して、モバイルバッテリーは最後の手段に残しておくことにしました。
スマホの電源さえ確保できれば、安心感は違ってくると思います。
初日の午前にスーパーで買い物
近所のスーパーは、停電のなかでも店を開けていてくれました。
停電でレジが止まっていたので、その店では1品100円で販売してくれていました。
長蛇の列で水などもなくなっていましたが、飲料と食べ物を少し購入できたのはありがたかったです。
1品100円では赤字だと思いますが、レジが使えないなかで柔軟な対応をしてくれたことは利用者の記憶に残ります。
今後、このスーパーは積極的に利用して、赤字分以上は利益還元してあげたいと思います。
食料の考え方
震度7と聞いて、物流が止まれば最悪の場合は数日は買い物ができないかも、と考えていました。
Twitterで流れていた考え方は参考になりました。
北海道で震度6強の地震があったと聞きました
2年前の3月11日に無印良品に行った際に配っていた紙が災害時に役立つ事が書いてあったので載せておきます pic.twitter.com/QDYin2a0kf— こーこん。 (@aska8nnmrk) 2018年9月5日
下のリンク先でPDFで見ることができます。こちらは参考になると思います。
参考になったのは食材の利用方法です。
- 最初の2、3日 →冷蔵庫内の食品
- その後 →レトルト・インスタント
正直、1日目の段階では停電がいつまで続くかはわからず、電力が全て回復するまで1週間という報道もありましたので、1週間は停電のなかで食いつなぐことも想定して食品を消費していました。
ですので、最初は冷蔵庫内の食品から使っていきました。冷蔵庫も不必要に開けないことで冷気を逃さないようにします。保冷剤などがあると色々便利です。
一時期、水道水の水の味が少し変に感じたので、鍋の水を使っていました。
冷蔵庫内と備蓄で1週間は持ちそうですが、断水したら水が足りなくなるな…とは考えていました。
電波の悪い時間帯も
スマホはネットにつながっていましたが、6日の夕方から夜にかけてはネットにつながりにくい時間帯もありました。
スマホでニュースは確認できましたが、一番利用価値があったのはTwitterでした。
見通しがつかないのは、一番不安になるところです。家族もどうなるか気にしていたのですが、経済産業省と北海道電力のツイートが見通しをたてるうえでよかったです。
子どものケアと早めの就寝
今回、運が悪いことに5歳の長男は地震の前から胃腸炎で体調不良でした。
そこに地震がきたので、停電のなか、ライトの光のなかで長男は嘔吐を繰り返していました。
「いつまで電気つかないの?…」と不安げなので、「大丈夫だよ」と声をかけながら、見通しをたてられるような話をしました。
地震後の子どもの精神的なケアは、結構重要かもしれません。
このような体調なので、夜にライトで過ごすのは賢明じゃないなと思い、日没で就寝するようなスケジュールで動くことにしました。
できるだけ子どもたちの寝る時間を長くする作戦です。なんとなくですが、早く寝ることで、子どもたちの不安を小さくする効果はあったと思います。
2日目の9月7日午前で電気回復
これは長期戦になるかもと思っていたところでしたが、2日目の午前で電気が回復しました。
今電気が復活しました!😆
— なるたく(loloinvestors) (@loloinvestors) 2018年9月6日
子どもたちが安心した顔を見せたので、早めに電気が回復したのは結果として助かりました。
今回の経験で足りなかったもの
防災用品を用意していても、いざというときに使えなければ意味がありません。
今回の経験で、防災用品で理想的なのは、普段から使っているものがそのまま非常時に役立つというパターンな気がしました。
今回、9月という季節は不幸中の幸いだったという気もしています。
これが真冬であれば、見える景色が違ってきます。おそらく、この程度の被害では収まらなかったのではないかと思います。
今回、北海道電力の現状を知ることになり、また地震があれば同じようなブラックアウトの可能性はゼロではないこともわかりました。
今回の経験で、わが家でも必要なものがわかってきました。
- 室内を明るく照らすLEDライト
- 電気を使わないストーブ
- 湯たんぽ、カイロ
- あたたかいウェアやインナー
今のライトでは、夜は暗くて安心感を生むような光を作ることはできないことがわかりました。
ちなみに、1日程度ならこんな工夫でも乗り切れます。
【夜を迎える前に要確認】
地震の影響で北海道の広い範囲で停電が発生中です。停電時に家を明るくするために役立つ方法を警視庁災害対策課がまとめているので紹介します。
(1)ペットボトルで簡単ランタン
(2)ツナ缶でランプ
(3)サラダ油で簡易ランプhttps://t.co/NTz1OHQYoU pic.twitter.com/q8RQEmU31p— ウェザーニュース (@wni_jp) 2018年9月6日
ただ、長期になったときには、今のライトでは不安な感じがしました。普段使いができて、もう少し強力なライトを用意しようと思います。
そして、北海道で必要なのは暖房対策です。
妻とは、家族全員がスキーウェアやアウトドア用のインナーを揃えようという話をしています。
暖房は悩みどころです。わが家は電気がとまると電気ストーブはもちろん、ガスストーブもストップします。
冬を想定すると、暖房の有無は生死に関わります。電気を使わない灯油ストーブを用意しておいたほうがいいのかもしれません。
ただ、北海道の家屋は気密性が高いことから、煙突がない灯油ストーブは推奨されていないことは道民の常識です。このあたりの暖房対策についてはもう少しリサーチしてみようと思います。
湯たんぽやカイロも冬までに用意しようと思います。
今回、電気がなくなって危機意識が高まりました。避難所などの外にでる場合には、また別にいろいろ必要になりそうですが、自分の家で防災しながら生活するには、この程度のものを用意しておけばなんとかなりそうな感じもしたというのが今回の経験です。
自分の生活は自分で守る
今回で実感したのは、自分の生活は自分で守るということです。
準備しておけば家族の不安を小さくすることもできます。この点はお金の資産運用と同じかもしれませんね。
まだ地震の影響は終わっていません。節電を意識しながら、日常を少しずつ取り戻したいと思います。
以上、北海道胆振東部地震で準備してよかったもの。足りなかったもの…という話題でした。
参考リンク:
現金を用意したりカセットコンロを用意したりしたのは、この記事を作成した頃です。東日本大震災の際の知恵は参考になります。