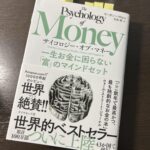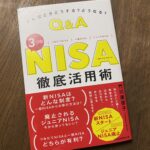2021/08/13

いつも愛読しているブログ「The Arts and Investment Studies」の菟道りんたろうさんの今日のエントリーは、リスク資産と無リスク資産の比率の話題でした。
リスク資産と無リスク資産のウエート管理に常に気を配ることで、リスクを管理されているという話です。ためになりますので一読をおすすめします。
リスク資産と無リスク資産の管理の方法について、私も頭の整理をしてみたいと思います。
sponsored link
目次をタップすると見出しにとびます
リスク管理にも流派がある?
リスク資産と無リスク資産の比率の話題になると、私はちょっと混乱したりします。というのも、リスク管理の仕方についてはいくつかのやり方があるように思うのです。いわば流派の違いがあると思います。
自分が知っている範囲では、大きく3つの流派があるような気がしています。
伝統の流派—アセットアロケーションに無リスク資産を入れる
私が投資をはじめた2012年頃の主流は、アセットアロケーションに日本債券クラスを加えることで、リスク管理をするという方法だったと思います。
カン・チュンドさんの書籍『忙しいビジネスマンでも続けられる 毎月5万円で7000万円つくる積立て投資術 (アスカビジネス)』にも、日本債券クラスで管理する方法が紹介されていますし、「梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー」の水瀬ケンイチさんも日本債券クラスをアセットアロケーションに加えることで、リスク管理をされています。
私も、このやり方で投資をはじめましたので、アセットアロケーション内に日本債券クラスを入れて、リスク管理を続けています。現在、日本債券クラスはインデックスファンドではなく、個人向け国債変動10年にしています。
このやり方の利点は、アセットアロケーションに無リスク資産があるので、ネット証券の口座にも無リスク資産が同時に表示されます。
この方法が好きなところは、視覚的にもわかりやすく、無リスク資産がクッションの役割を果たしてくれることです。暴落時にも、ネット証券内のポートフォリオでは下落幅が抑えられていることが実感できます。
最近の主流—全資産でリスク資産と無リスク資産を管理する
一方、最近主流になりつつあるのは、全資産のなかでリスク資産と無リスク資産を管理する方法です。
菟道りんたろうさんがそうですし、「インデックス投資日記@川崎」のkenzさんもこの方法です。お二人とも、リスク資産と無リスク資産の理想とする配分比率は50:50にして、リスク管理をされています。
横山光昭さんの「はじめての人のための3000円投資生活」で紹介されている、バランス型投信と貯金を組み合わせる積立投資も、この考え方がやりやすいと思います。
アセットアロケーションに日本債券クラスを組み入れない方や、バランス型投信1本で積立投資をする方は、この方法がいいのかもしれません。
全資産を把握すれば、わかりやすくリスク管理ができます。
この方法だと、相場下落時には頭のなかで資産全体のなかでの下落幅を再計算することになります。頭のなかで計算をすることで、安心を勝ち取るイメージです。
組み合わせ型—ダブルで無リスク資産を持つ
最近、個人的にいいかもしれないと思っているのは、カン・チュンドさんがブログで紹介されている方法です。
投資にまわさないお金を持ち、さらにアセットアロケーションのなかにも無リスク資産を持つという方法です。
コンサルティングのなかでは、次のように説明されているといいます。
1.無リスク資産、
すなわち、投資に回さないお金を持つ。
さらに、
2.投資に回すお金(ポートフォリオ)の中でも
無リスク資産(安全資産)を持つ。
という【アドバイス】を行っています。
リンク先のカン・チュンドさんの記事は必読です。はじめての方にも参考になると思います。
リスク資産と無リスク資産の比率で管理する
やはり、どの方法でもリスク資産と無リスク資産の比率で管理するということになります。
私はアセットアロケーションのなかに無リスク資産があったほうが安心できます。投資をはじめた時期に刷り込まれた考え方ですので、どうもやめる気になれません。
自分の場合は、1番目の方法で投資をはじめましたが、最近は3番目の方法で整理するのがいいかなと思っています。
私の現状を紹介すると、こういうリスク管理になっています。
アセットアロケーション内で3割の債券クラスを持っています。日本債券クラスには個人向け国債変動10年を入れています。
そして、投資にまわさないお金(生活費2年分の生活防衛資金と預貯金)と投資にまわすお金(日本債券クラスを含む)の比率の基本は5:5で考えています。
現時点では、投資にまわさないお金が6、投資にまわすお金が4といった割合です。
預貯金には、生活費や出費用のお金も含まれていてそれなりに変動しますので、あまり厳密に考えず、ざっくりと把握しておいて、臨時の収入があるときなどにバランスを確認するといったやり方がやりやすいような気がしています。
大事なのはおおざっぱにでもバランスを維持して、無リスク資産を割合的に保持することです。
菟道りんたろうさんが言うとおり、無リスク資産こそ、個人投資家を相場の荒波から守ってくれる最後の防波堤です。
そうなんです。私もかなりの慎重派なのです。
以上、リスク資産と無リスク資産の比率でリスクを管理する…という話題でした。